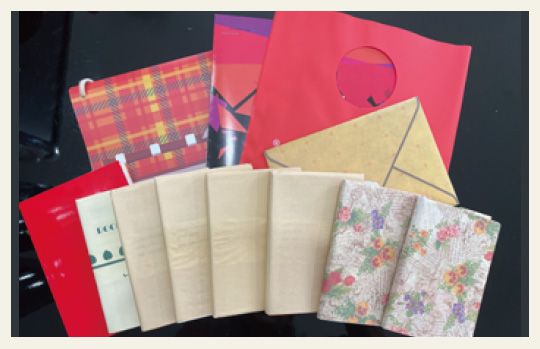小学生の時にエラリー・クイーンの国名シリーズに出会い、ミステリー小説や探偵小説を読むのが好きになった。最近は積読(未読のまま積まれた状態)になりがちだが、気になる小説があるとつい購入してしまう。緻密なプロットを味わいながら意外な真相を突き止めるべく、様々なパーツを組み立てながら読み進めていくのはとても楽しい時間である。そういった意味で、リアル謎解きゲームや脱出ゲームも好きである。
こういった小説において、科学は重要な役割を果たしてきた。例えば、19世紀のシャーロック・ホームズシリーズでは当時の新しい科学技術が多く取り入れられ、20世紀半ばのアガサ・クリスティの作品では毒物の知識が頻繁に用いられた。21世紀に入ると、DNA解析やAI、サイバーセキュリティといった最先端の科学技術がトリックの鍵となることが増えている。このように、ミステリー小説における科学技術の活用は、科学技術の進歩を反映しているとも言える。
科学技術コミュニケーションにおいては、常に進化し続ける科学技術をどのように伝え、社会が科学技術をどのように捉えていくか、科学技術と社会とのつながりを考えていく必要がある。そういう意味では、最新の科学技術を取り入れた小説を通して、科学技術が日常生活にどう影響するのかを伝えることができるかもしれない。一方で、小説では現実の科学技術や社会とは異なる形で提示されることもある。従って、科学技術コミュニケーションの文脈では、科学的事実と物語の境界を理解し、正確性を保ちながらも、科学技術と社会との関係を親しみやすい形で伝えていくことが求められる。
科学技術は時代と共に変化し続けるため、それを題材にした小説や謎解きゲームのトリックもまた変化を続けるだろう。小説やゲームを楽しみながら、科学技術と社会との適切なつながりについても考えていきたいと思う。